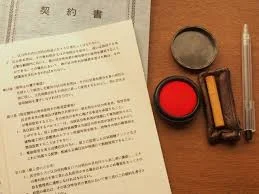さて物流コンペを実施し、契約書に調印する段階になってきました。その時にぜひ盛り込んだ方が良いのでは?という事項を紹介します。一般的には別紙のSLA(サービス・レベル・アグリーメント:サービス品質保証)を順守するという形にするのが多いです。SLAだけを順次更新するのを想定しての形態です。
契約期間:
2年間としてその後自動延長。解約の場合は2ヶ月前の末日までにお知らせする。というような例でコメントするなら、特に設備投資をしなければ2年間は長過ぎ、何か問題があった場合に他に逃げるという選択肢が0になるのは避けたい。また解約のお知らせをしてから引っ越しまでの期間(この場合2ヶ月)はできるだけ短くしたいです。契約打ち切りが決まって、現行3PLがモチベーション低いままオペレーションを実施するのは問題があり過ぎます。
入出荷:
入荷であれば、着荷してから*時間 or *日以内に実施する。出荷であれば、営業日当日15:00までの注文引き渡しは当日中に出荷する等です。
在庫管理:
細かいアクセサリーや高価な商品は棚卸しの際に紛失が判明します。在庫管理の責任を担保してもらうために**%以上の紛失の場合は下代を掛けあわせた金額を保証する。
料金形態:
そこそこの規模になると、専任のチームを設けたい。敷いては入荷 1人(**万), 出荷(**万), 全体の管理するマネージャー(**万)というのを工数の見積もり(入荷 **円/点,出荷 **円/点)とは別に3PL側は用意してきます。容赦なく断りましょう。規模が大きくなると、どんどん専任の人を増やしたいと3PLが言い出し、どんどん固定費が増えます。そもそも3PLに業務委託する目的は変動費化することだということを忘れてはいけません。現実的にそういった人がいないと現場は回らないので、料金として考慮することになり、各々の工数に付加して料金を出してもらいます。
レポート:
業務の量がそれほどでもないと良いですが、それなりになってくるとバックログも考慮しないといけなくなってきます。それらを把握するためにレポートを作成してもらいましょう。3PL側で請求するにあたって、各々の作業項目*量は請求用につけているはずなので、それをベースにするのです。原始的ですが、毎日excelでつけた帳簿になる3PLがほとんどです。特定の項目の達成率を蓄積したDBから必要な項目を自動で抽出するなんてことはないです。